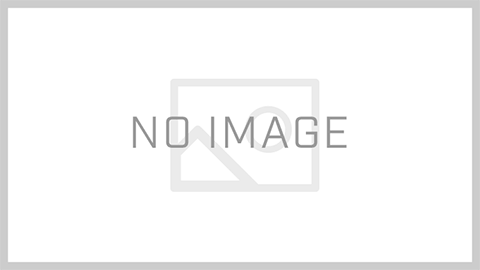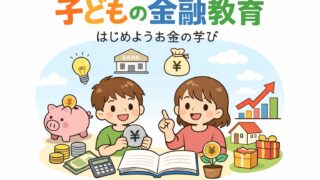育休中の家計~収入減でも安心!楽しく乗り切る家計管理術~
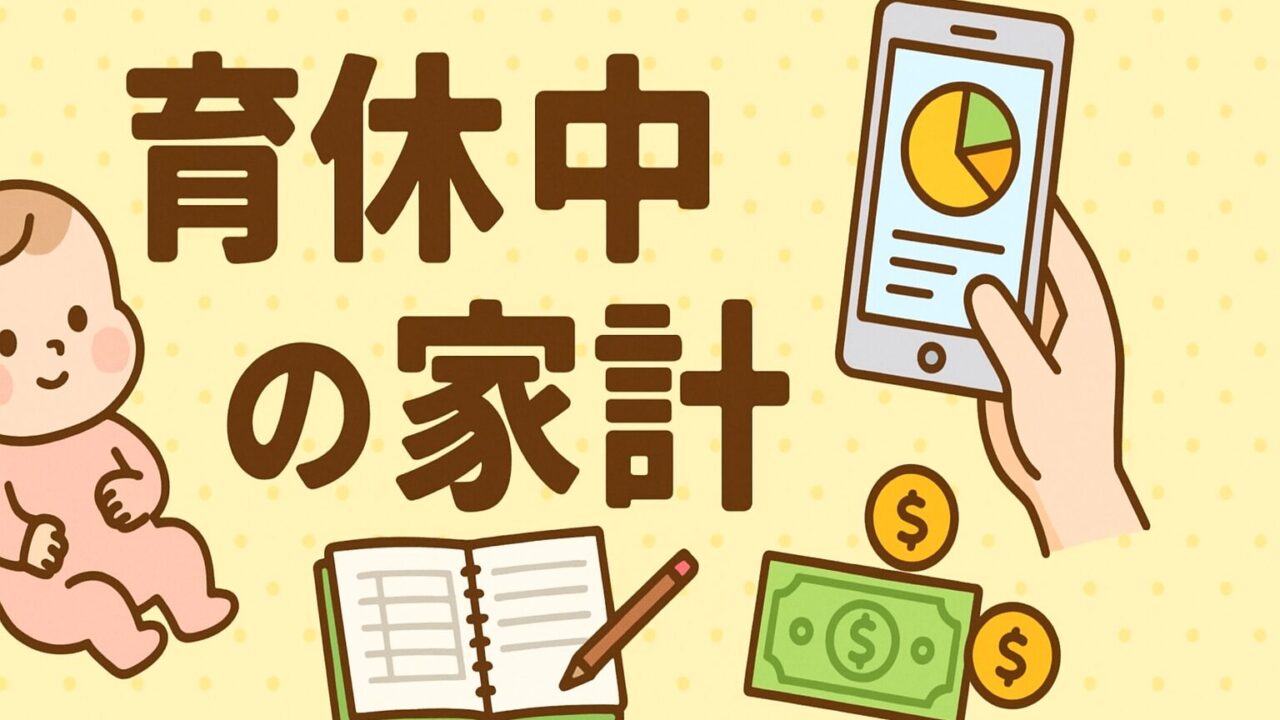
Contents
はじめに:育休とともにやってくる“お金の現実”
赤ちゃんが生まれると、毎日が新しい発見の連続。
例えばお金。
「あれ?口座の残高、ちょっと減ってない?」と、ヒヤリとする瞬間も。
育休中は、収入が減る一方。
オムツ・ミルク・ベビー用品など支出は右肩上がりです。
でも安心してください。
家計の全体像を「漏れなく把握」できれば、焦らず穏やかに過ごすことができます。
この記事では、育休中の家計管理をラクにする考え方と実践法を紹介します。
育休中の収入はどうなる? まずは全体を見える化
まず最初に確認したいのは、「お金がどこから、いくら入ってくるのか」です。
一般的に、育休中の主な収入源は次の3つです。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金 | 雇用保険から支給(給料の約67%→180日以降50%) | 非課税 |
| 社会保険料免除 | 育休期間中は健康保険・年金の支払いが免除 | 実質的な支出減 |
| 児童手当など | 月1〜2万円の定期支給 | (自治体によって)所得制限あり |
ポイントは、「給付金が支給されるまでに1〜3か月のタイムラグがある」こと。
この期間は、貯金を切り崩すことになるため、キャッシュフロー(現金の流れ)を把握しておくことが重要です。
家計管理のコツ:「見える化」と「自動化」
「育休中は節約が命!」と思われがちですが、
実は“管理の仕組み化”こそが最強の節約術です。
おすすめは、家計管理アプリの活用。
代表的なものには「マネーフォワード ME」や「Zaim」「Moneytree」などがあります。
銀行口座・クレジットカード・電子マネーを連携しておけば、支出を自動で分類・集計してくれる優れモノ。
しかも、「食費」「日用品」「ベビー用品」などカテゴリごとの支出割合もグラフ化されるので、
「今月はおむつ代が先月より1,000円増えてる!」と“家計の変化”を漏れなく把握できます。
さらに、アプリの自動連携機能を使えば、「レシート入力」という地味な手間からも解放。
育児の合間にスマホでチラッと確認するだけでOKです。
節約より“取捨選択”。必要経費は罪じゃない!
育休中は、家計を締めすぎるとストレスが爆発します。
「毎食手作り」「光熱費はギリギリまで我慢」…そんな完璧主義は長続きしません。
むしろ、「どこにお金をかけるか」「どこを削るか」を意識することが大切。
例えば──
- ✅ おむつ・ミルクはまとめ買いでポイント還元を狙う
- ✅ 食洗機や乾燥機など“時短家電”は投資と割り切る
- ✅ サブスク(動画・音楽)は1つに絞る
「節約」ではなく、「効率的なお金の使い方」を意識すると、
家計にも心にもゆとりが生まれます。
共働き家庭は“チーム家計”を意識しよう
育休中は、片方の収入に頼ることが多くなりますが、
「家計=夫婦の共同プロジェクト」
という意識が大切です。
例えば、次のような役割分担もおすすめです。
| 役割 | 内容 |
|---|---|
| パパ | 収入・給付金・税金関係を管理 |
| ママ | 日常の支出や生活費の管理 |
| 共通 | 家計アプリで全体の収支を共有 |
アプリを共有すれば、家計の「見える化」が夫婦で同時にでき、
「なんでこんなに食費がかかってるの?」という不毛なケンカも減ります。
“いま”を楽しむことが最大の投資
育休中は、経済的には少し厳しい時期。
でも、長い人生の中では「今しかできない時間」でもあります。
お金の心配ばかりしていると、せっかくの育児の喜びが半減してしまいます。
だからこそ、「使う」ときは笑顔で使いましょう。
例えば、
- 記念撮影の写真館代
- 家族でのお出かけ費用
- 育児グッズや家電
これらはすべて「幸せの記録」への投資です。
まとめ:見える化・自動化・チーム化で“ゆとり家計”を!
育休中の家計管理のコツは、この3つに尽きます。
- 見える化:収入と支出をアプリで把握
- 自動化:手間を減らして継続可能に
- チーム化:夫婦で共有して連携強化
家計は我慢大会ではなく、家族の未来をつくる共同作業。
「お金を管理する」のではなく、「お金と仲良くつき合う」。
そう考えれば、育休中の家計もきっと前向きに楽しめるはずです。
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。